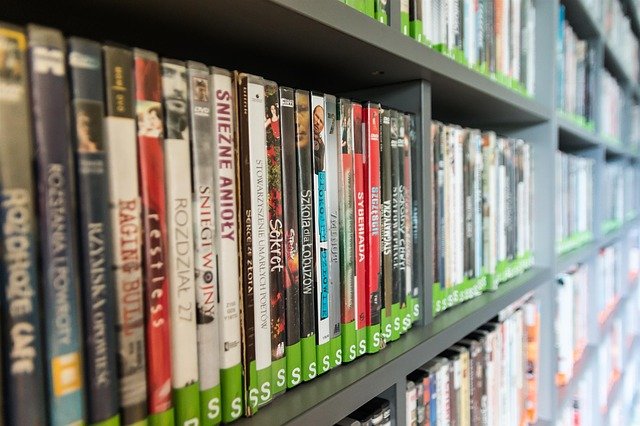これまでは軽いアップハンドルで乗っていたのですが、ジョッキーシフト化した事で乗車姿勢が変わったのをきっかけに、よりアグレッシブなスタイルに変更するため、ハンドルをタコロボ(Zバーにタコ膜状のプレートが付いたタイプ)に変更しました。
参考記事
検討の末・・・
取り付けた車種はYAMAHAビラーゴ250。
・・とは言っていますが、本当はビラーゴコピーのLIFAN250。しかもトライクです。
とりあえずハンドル部分のみの話ですので、二輪でも三輪でも共通という事で。
各タイプを検討した末に選んだのはこちら。
クラシックファクトリーのタコロボ(HIGH)です。
昔はロボハンのカクカクしたルックスがカッコ悪いと感じていたのですが、人は変わる物。歳を経てみると、曲線でアップされたハンドルよりも男らしい気がしてきました。
そしてジョッキーシフトは「ゆったりとふんぞり返って乗る」よりも「やや前傾姿勢」のほうが攻撃的で操作の楽しさも増します。
セルフ取り付け派の鬼門・配線通し
ミニスイッチなどを使用している場合、ハンドルバー内に配線を通さねばなりません。この作業が初心者殺し。
ゆったりとした曲線のハンドルであれば容易なのですが、角度が90度に近くなるとキツくなります。ましてや、Zバーはそれ以上の角度。
私は以前やっていた仕事柄、「細い内部に配線を通す」という作業はかなり経験を積んでいましたので・・・バイクハンドルの配線通しも得意です。
写真無しで恐縮なのですが、私のやり方をご紹介しておきます。参考になれば幸いです。

こちらはもう通した後の写真になります。左手側にウインカーとホーン(合計5本)、右手側にセル(2本)、それを中心まで引っ張り、まとめて9mm径の穴から出しています。
両手を使ううえに一度手を付けたら通しきるまで離せない作業なので、一人では作業中に撮影できませんでした。文字だけでは意味がないと思いますので、後程写真撮影のためだけにもう一度通します(笑)
使用するのはボールチェーン。
太いもの、細いもの、どちらにもメリットデメリットがあります。私は2mmくらいの玉を使っています。
これをIN穴から送り込み、OUT穴から出し・・・その先に配線をテープで巻き付け、引っ張って抜いて通す。
というやり方になります。
言葉で言うと簡単ですが、コツが必要です。注意する点を挙げておきます。
ポイントごとの注意点
チェーンの送り方
ボールチェーンは、その自重で送ります。重力を利用して、スルスル・・・と落としていく感じです。
なめらかなハンドルであれば簡単に先に進んでくれますが、Zバーのように角度にクセがある場合は難しくなります。
ボールチェーンをクイックイッとわずかに引っ張り戻しながら、トントンと振動を与えて少しづつ先へ進ませます。
穴から抜く
反対側の穴にボールチェーンの先が見えたら、そこから抜くのですが・・・その際はピックアップツールを使用すると楽です。

このような物です。
先端から爪が飛び出して掴めるようになっています。
配線を固定する
抜けたボールチェーンの先に、テープで巻いて配線を固定します。このテープの素材と巻き方が重要になります。
弱いと途中で外れますし、しっかり巻きすぎてもカーブや穴を通らなくなります。
まず、ビニールテープなどは論外です。私はいつも紙製のマスキングテープを使っています。
引っ張り戻す
ボールチェーンを引っ張って戻す際も、ぐいーっとそのまま引っ張ってはいけません。
トンッ・・トンッ・・・と、振動をかけるように引っ張り、時々反対側の手で、配線側のほうも同様にトンッ・・トンッ・・と戻します。
引っ張ったり戻したりを繰り返しながら、少しづつ送っていきます。
Zバー独特の注意点
1本のパイプを曲げて作られたハンドルバーであれば、どんなに長かろうと角度がキツかろうと、配線通しの難易度は低いです。コツさえわかれば、数分で終わる作業です。
・・・・が、ロボハンやZバーは全く別物。
曲がり部はパイプを切断して溶接されているので、パイプ内側にバリが大きく出ている事があり、これにボールチェーンや配線がひっかかります。
さらに90度超えの角度で曲がっているZバーでは、ボールチェーンが全く進まなくなったり、引っ張りだす途中で配線が抜けたり・・といった事が多々あります。
どんな形状、長さでも不可能ではありません
このタコロボの配線中通しについて他ブログ等で拝見したところ「LOWでも至難。高さ1インチのHIGHは不可能」とされていました。
でも決して不可能ではありません。HIGHのタコロボ、しかもパイプ系22.2Φの細いハンドルでも、自力で配線中通しは十分に可能です。

私の場合、穴空け作業も含めて約1時間の作業でしたが、慣れていなければ「無理だ・・」と諦めたくなるほど時間がかかるかもしれません。
配線の中通しは根気の勝負です。工具をブン投げたくなる作業ですが、ぜひ挑戦してみて下さい。
コツを掴んでしまえば、どんなハンドルでも通せるようになります。(中がしっかり空洞になっている物のみ、ですが・・)
後程、しっかりと作業中の写真を細かく掲載して再度記事にしますので、お待ちください。